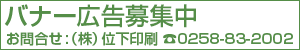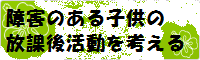東京電力福島第1原発から北に約25キロ。東日本大震災で大きな被害を受けた福島県南相馬市の原町中央産婦人科医院で、末期がん患者でもある高橋亨平(きょうへい)院長(74)が、厳しい闘病生活を送りながら、週1回のペースで診療を続けている。5月には「余命半年」の宣告を受けた。それから約7カ月たった師走。確実に迫る死を意識しつつ、今も復興への思いを絶やすことなく活動している。(西尾美穂子)
◆激しい副作用
約2時間の昼休みが終わり、午後2時から始まった午後の部の診療。淡いピンク色のじゅうたんが敷かれた院内を、看護師がせわしなく動き回り、待合室にいた数人の患者を次々に診察室へ案内し始める。
「今日はどうしましたか」。白い椅子に深く腰掛けた老医師は、優しくささやくような声で患者に話しかけると、患者の病状や悩みにじっくり耳を傾けた。
震災から2カ月後の昨年5月、大腸がんに侵され、肝臓と肺にも転移していることが判明。今年5月末には医師から「余命半年」の宣告を受けた。
宣告を受けたときと比べて体重は激減。診察の機会は日を追うごとに少なくなり、別の医師に任せることも多くなった。しかし、今でも週1回、数時間のペースで診療を続けており、本人が診察する時間帯は、患者がにわかに増える。
「今日は、亨平先生に診てもらえる」。“噂”を聞きつけた住民が集まってくる。分娩(ぶんべん)は11月以降、行っていないが、つい最近も、妊婦に「ここで産みたかった」と泣かれた。
数週間に1回程度は、片道約60キロの福島市にある病院に向かい、抗がん剤治療を受ける。診療中に、ポロシャツの胸ポケットに抗がん剤入りの容器を忍ばせ、伸びた管の先の針から絶えず体内に薬を投与することもある。足には冷えを防ぐための靴下を3枚履き、薬の副作用で時折、どっと出てくる汗を首にかけたタオルでぬぐう。
痛み、吐き気、倦怠(けんたい)感…。患者を診ていると、ふと「私の方がつらいんじゃないか」「重症人が健康人を診ているのではないか」と思うこともある。だが、患者には心配をかけたくない。診療では「悟られないように」と平穏を装う。
◆最後のお願い
震災後も、がん発覚後も南相馬市にとどまり診療を続けた。「人間である以上、つらいなんて言っていられない。震災で亡くなった人を思えば、私はまだまし」。今もその覚悟は変わっていない。
しかし、病魔は容赦なく老体に襲いかかる。
8月初め、「体中がしっちゃかめっちゃかになるような」すさまじい副作用に襲われた。吐き気が止まらず一晩で体重が3キロも減少、「一つ一つの細胞がしぼんでいく感覚」を覚えた。「こりゃ重篤だ。いつ死んでもおかしくないな」。このころから、死をはっきりと意識した。
同月中旬にインターネットのホームページで自分の現状を訴え、“私の最後のお願い”として後継者を募った。「この地域でも、子供たちに賢く生きれば安全に生きられることを教えてあげられる人間味のある医者に引き継いでほしい」
訴えから約3カ月後の11月、願いは届き、来年から新たな男性医師(43)を常勤として迎えることが決まった。震災以降自らに課した「南相馬の医療を守る」という役割は一段落し、一つ肩の荷が下りた。
残るは復興への思いだ。8月にほかの医師とともに設立した放射能の除染方法について話し合う研究会に今も参加。若手の育成や被曝医療の発展について率直に意見する。
「南相馬、そして日本の復興のため、まだまだやり残したことがある」
心に宿した情熱は、まだまだ消えることはない。
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20121225093.html