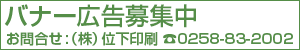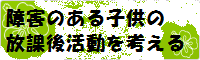巨大な堤防が壊され、陸側は一面、がれきが広がる―。東日本大震災の被災地に入って2日目の29日、私たちは宮城県から東北自動車道を北上し、岩手県山田町を訪れた。漁業が主な産業で、海の恩恵を受けて発展してきた町だが津波で大きな被害を受けていた。 (湯川優史、中陽一)
午後1時50分、町役場に着いた。まちの中心部、海岸から500メートルほど離れた山際にあり、被災をまぬがれていた。屋上から街並みを見る。悲惨な状況を目の当たりにすると同時に、異様な静けさにも気付いた。
耳に入ってきたのは、車が走る音と、時折上空を飛ぶ自衛隊のヘリコプターの音。カラスの鳴き声。「街の音」がまったく聞こえなかった。
役場を出て周辺を歩く。自衛隊員が消石灰をまいている。車は通れるようになっているが、建物があった場所は、がれきの山。粉じんが舞ってマスクなしでは歩けない。
震災前は、どんな街並みだったのか。
「ここは商店街。向こう側は、漁師が集まる飲み屋街があったんだ」。そう教えてくれたのは、仮設の派出所の建設作業中だった佐々木明さん(42)。辺りでは火災も発生したが、消火活動ができず、まちは1週間近く燃え続けたという。
海の方に向かうと、高さ4、5メートルはある堤防が破壊され、すぐ前の建物をつぶしていた。陸には、打ち上がった漁船が数隻あった。
役場近くで民宿を営んでいた山根勝郎さん(69)は、間一髪で津波をまぬがれた当時の様子を振り返った。「自宅前の通りに出ると、海の方から建物が丸ごと波に押し流されて来るのが見えた。何も持たず、とにかく走って逃げた」。想像しただけで、恐怖心が体中を駆け巡った。
役場に戻ると、罹災(りさい)証明や仮設住宅の申し込みなどの手続きで訪れた町民で混雑していた。
ロビーには、伝言板があった。「どこにひなんしているの」「連絡待ってます」。家族や知人の安否を気遣う気持ちが、ひしひしと伝わる。
午後3時半。役場隣の保健センターでは、パンや牛乳、カップ麺などの配布が始まるのを待つ町民が、数百メートルの長い列をつくっていた。
●和歌山の医師が活躍
役場から車で内陸に走り約20分。和歌山県医師会のチームが27日から30日まで支援に来ている避難所の豊間根中学校を訪ねた。多くの人が避難生活を送る体育館のそばを抜けると、「相談室」と札のかかった部屋が仮の診療所となっていた。避難所が開設されて以降、県内の医療機関が引き継ぎながら運営してきた。同チームは医師2人のほか、看護師、薬剤師など計10人で運営にあたった。
そのなかに田辺市から来た医師の水本博章さん(62)の姿があった。外来は毎日20人ぐらいいて、往診もある。大けが、大きな病気というのではなく、これまで飲んでいた薬がなくなった、処方してほしいという求めや、避難している人たちの健康上の問題などに対応しているという。「もともと地区には医療機関がなく、受診に来た人の『ありがとう、ご苦労さんですね』という言葉が印象的です」と語る。
この診療所も30日には閉め、その後は訪問診療に移るという。水本さんは「実際現場に来ると、うなるしかない。医療も社会基盤がある程度整っていてできるもの。地元の医師の中には、亡くなられた人もいるが、最近になって少しずつ日常の診療も再開されてきた。これからは、地元の医師に診てもらえるように、側面から応援していく方向になる」と話した。
◇
町によると28日現在、収容した遺体は580体。378人の行方が分かっていない。31カ所の避難所で、計約2800人が生活している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110430-00000002-agara-l30