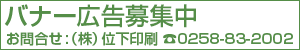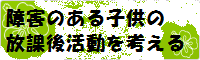家族水入らずで3年ぶりの海水浴を楽しむはずだった。「やっぱり、いやだ。行きたくない」。強い日差しが照りつけようとしていた夏の朝、岩手県宮古市の市立小2年、山根絆那(はんな)さん(7)は父親の服の袖をつかみ、震えながら急にぐずりだした。
「波の音を聞くだけでもいや」
東日本大震災の日、黒い水がゴーッという音とともに、建物をのみ込みながら、自宅数メートル手前まで襲いかかるのを目撃した。「海は怖いもの。絶対に近づかない」。いつも笑顔を絶やさないが、海に話が及ぶと途端に表情を曇らせる。
姉で市立小5年の璃姫(りこ)さん(11)は最初の揺れの直後、学校裏の神社に避難した。津波は見ていないが、津波が「バキバキ」と建物を押し倒していった音が耳に刻まれている。
姉妹は震災前まで愛犬の散歩コースだった海岸に、いまでも近づこうとしない。自宅から坂道を約100メートル下りれば、目と鼻の先に海岸が広がる。だが、そこでコースを変え散歩を済ませる生活が2年半続いている。
「実際に行って海が悪いところじゃないと教えたかった。この子が海を楽しめる日は来るのか」。父親で消防士の誠司さん(38)は愛娘(まなむすめ)たちの小さな胸に刻まれ癒えないままの傷を思い、ため息をついた。
◆不登校や問題行動も
震災時、多くの児童や生徒は学校などにいたため、教諭らの指示で避難し助かったケースは多い。だが、その際に目撃した光景や家族と友人の喪失、自宅や学校の損壊が与えた精神的なダメージは深刻だ。
岩手県は小児科医が慢性的に不足していたため、震災から3カ月が経過した平成23年6月、津波による被害が甚大だった沿岸部の宮古市で児童生徒と保護者を対象にした精神ケアを開始。釜石市や大船渡市でも同様の出張所を開設した。診療のために訪れた児童生徒は2年間でのべ722人に上った。
「津波を見て以来、水が怖くてプール授業の季節になると学校に行けなくなる」「逃げる最中に自分だけが遺体を見たと思い、黙っていたら毎晩悪夢にうなされるようになった」「震災前に母親とけんかをして『死んでしまえ』と言ったせいで母親が亡くなったと自分を責めてしまう」-。
トラウマを抱えながらも家族に相談できず不登校になったり、問題行動を取るケースは後を絶たない。
◆「誤った認識」で苦悩
「大人から見れば思い込みにすぎないが、子供は幼いままの理解度で間違って記憶してしまう」。そう指摘するのは、5月に子供の心のケアを担う拠点として岩手医科大(岩手県矢巾(やはば)町)にできた「いわてこどもケアセンター」副センター長の八木淳子医師(45)=児童精神医学=だ。
センターには児童精神科医や臨床心理士らが常駐。週に1度、宮古、釜石、大船渡で出張診療する「沿岸ブランチ」も行う。診療に訪れる児童生徒の中で、震災で肉親などを失いトラウマを抱えた子供は1割ほどにすぎない。9割は震災前に未診断で、学校や地域の環境変化で生活に適応しきれなくなり顕在化したケースだという。
だが、センターの常駐医師は1、2人で子供1人に最低でも30分をあてるため、1日10人ほどが限界。再診も多く、新たな診療に応じにくい。
八木医師は「元気に見えても、2年半の間に思い出さないようにしてきた結果、言い出しにくくなっている子供たちも多い。成長して正確な理解が進む場合がある一方で、誤った認識のまま、より深く苦悩する場合もある」と指摘した。
【用語解説】被災3県の子供の心のケア
「いわてこどもケアセンター」のほか、宮城県は震災直後、「子ども総合センター」の児童精神科医を沿岸部に派遣。乳幼児健診でも臨床心理士が相談に対応している。福島県は児童相談所に児童精神科医を派遣している。このほか、東京電力福島第1原発事故による避難者が多いことから、県内外で避難者の母子が集まって悩みを相談し合う「話会(わかい)」を開いている。
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/life/education/snk20130918513.html