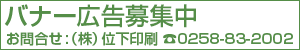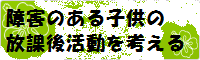【服部誠一】豪雪地に伝わる「越冬食」を真のグルメとして見直そうという動きが、十日町市で活発化している。山菜、野菜、木の実をもとにした冬の保存食で、地元タクシー会社社長村山達三さん(68)が「雪国の過酷な暮らしを生き抜いてきた先人の知恵を伝えたい」と、4年前からこつこつと呼びかけてきた。
11月21日夜、十日町市の道の駅「クロステン」ホールに90品目以上の郷土料理がずらりと並んだ。トチノミやオニグルミといった縄文時代からの木の実食材、自然薯(じねんじょ)のとろろ汁、ナラタケ入りのもぐら汁、ムカゴの塩ゆで、ケンポナシやヤマブドウの果実酒……。
ほとんどは越冬食。自然の恵みそのままのメニューは、市内の山菜農園や料理クラブなど食にかかわる18チームが持ち寄り、「越後妻有の自然を食う会」として初めて催した試食会だった。県や市、鉄道会社からの参加者が舌鼓を打つ中、スタッフらは「新たな食産業に」「雪国の食文化を伝える活動にしたい」と張り切っていた。
会は、村山さんが2010年から年1回、2月の第2土曜に個人で開く「松之山郷の自然を食う会」が母体。市内全域に活動が広がったものだ。村山さんは、北越急行ほくほく線沿線を活性化させるNPO法人を05年に立ち上げ、会員特典として「食う会」を考えた。
松之山郷(旧松之山町・松代町)は毎冬、3メートル以上の雪が積もる。松之山温泉の出身で8人きょうだいの三男坊だった村山さんは、暖房用の薪(まき)を拾いにいく山中で、アケビやヤマブドウを採った少年時代をよく覚えている。「雪消えとともに次の越冬を考える。冬の食の備えはどこでもしていた」。天ぷらなど口にしたことはなく、降雪前に街中に買いにいくイカの丸干しやシャケ、みがきニシンがぜいたく品だった。
村山さんが越冬食文化を伝えたいという思いは、近年のグルメブームへのちょっとした反発でもある。「お金さえあれば何でも手に入る時代。生きるために食わなければならないという食の原点を見失わないようにしたい」と話す。中越地震などの大災害が相次いだこともきっかけだ。
村山さんの自宅1階の倉庫にはタケノコや自然薯、クルミ、ゼンマイ、果実酒などの越冬食が所狭しと並ぶ。初春から晩秋にかけ、仕事の合間に採ってきた山の幸だ。「A級やB級グルメというが、こちらは永久グルメ。サバイバルに必要な本当の料理ですよ」
http://digital.asahi.com/articles/TKY201312130310.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201312130310