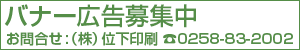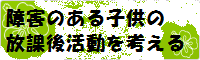胎児がダウン症かどうか、高い精度で分かる新型の出生前診断が、近く国内の約10医療機関で試験的に始まる。
最新の生殖医療技術が「命の選別」を助長するような事態は、避けなくてはならない。
安易な実施に歯止めをかけるため、日本産科婦人科学会などは、検査する際の基準を規定する指針の作成を急ぐべきだ。
妊婦の血液から胎児の染色体異常などを調べる出生前診断では、既に「母体血清マーカー」と呼ばれる検査法が普及している。
厚生労働省は「医師は勧めるべきではない」との見解を出しているが、強制力はなく、年間2万件近く実施されている。異常の可能性を知って、妊婦がショックを受け、人工妊娠中絶を選択するケースが少なくないとされる。
ダウン症の発症を確率でしか予測できない旧来の方法に比べ、今回、試験的に始まる新型の診断法では、ほぼ確実に判定できる。専門医などの間で、「安易な中絶を助長する恐れがある」との懸念があるのも当然と言えよう。
新型診断を導入している海外では、「障害者の排除につながる」として、家族らの団体が反対声明を出し、国際刑事裁判所に提訴した例もある。
出生前診断が広まっている背景には、晩婚化に伴い、先天疾患のリスクが高まる高齢出産が増えている現状がある。「赤ちゃんの障害の有無を知りたい」という妊婦の依頼を、医師はなかなか断れない実情もあるのだろう。
医師は、検査を要望されたら、ダウン症の正しい知識を丁寧に説明することが大切だ。
ダウン症は知的障害や心疾患を伴うことが多い反面、医療や教育体制が整備され、多くの人は健やかに日常生活を送っている。
妊婦の不安に応えるカウンセリング態勢の充実が欠かせない。現在、全国で約270人の専門家を増やしていく必要がある。
米国では今年6月、妊婦の血液と父親の唾液から、胎児のすべての遺伝情報を解読することに成功した。実用化されると、ほとんどの遺伝性疾患を胎児の段階で調べることが可能になる。
そうなれば、医療現場には今後、さらに重い課題が突き付けられよう。今回の新型診断は、その入り口に過ぎないと言える。
生殖医療の技術革新に、利用や規制のルールが追いついていないのが現状だ。指針の作成においては、将来の技術の進展も見据えた議論が求められる。
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/life/medical/20120908-567-OYT1T01202.html