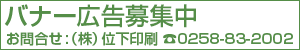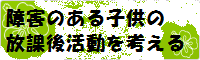他者に無関心な都会と違って、遠慮も配慮もなく、言の葉をダイレクトにぶつけ合う場を田舎と呼ぶのだろう。言葉のドッヂボール。無骨さに募る苛立ち。閉鎖的な空間で感じる息苦しさ。だが、その場に生きる人に支えられることもある。第152回芥川賞を受賞した小野正嗣氏の『九年前の祈り』は、大分県にある集落を舞台に、そこで暮らす人々を描いた物語だ。母親の葛藤を描いた表題作を軸として、4作の短編がゆるやかにつながりあい、奥行きのある世界を描き出している。
表題作の主人公は、カナダ人の夫と離婚した、35歳のシングルマザー、さなえ。彼女は息子の希敏(ケビン)とともに故郷に戻ってきたが、地元の者たちは、彼女よりも「ガイコツジン」の元夫に似た顔を持つ希敏に好奇の目を向ける。一度泣き出すと収拾がつかなくなってしまう息子をもてあましながら、さなえは、9年前、ともにモントリオールを旅行した「みっちゃん姉」こと渡辺ミツの言葉を思い出す…。過去の旅行の記憶と現在という時が絡み合いながら、2人の「母」の思いが次第に重なり合っていく。
さなえの息子・希敏はどうも表情に乏しい。かと思えば、少し環境が変化するなど、何かのスイッチが入ると、「引きちぎられたミミズ」のように発作的にのたうちまわり、泣きわめく。母親としては、障害とはどうしても認めたくない。しかし、受け入れなくてはならないのだ。いくら反応に乏しい子だとしても、息子と毎日向き合わなくてはならないのだ。自分の子は無条件に可愛いが、しかし、同時にとてつもなく憎い。そんなアンビバレントな感情を、混沌と心に浮かぶ母の葛藤を、小野氏は読んでいるこちらが痛々しく感じるくらいありありと描き出していく。
小野氏の描き出す表現は、すべて悲しくも美しい。幾度と繰り返される「引きちぎられたミミズ」の表現は賛否両論あるようだが、息子と向き合わなくてはならない母親にはやはりどうしてもそう見えてしまう瞬間があるのだろう。「鳥の群れが一斉に飛び立つように」笑う田舎の女たちと、地をのたうつ「ミミズ」の息子。さなえは、天を見上げるように田舎の女たちとの旅行を思い出すのだ。
「子どもはみんな泣くものだ。うちの子も泣いてのお。いくらあやしても泣きやまんかった。どげえしても泣きやまんかった」。
さなえが地元で唯一信頼を置いていたミツの言葉が彼女の中でこだまする。ミツもまたさなえと同じように思い悩んでいたのだろうか。今も悩んでいるのだろうか。さなえと希敏はこれからどうなっていくのだろうか。
「悲しみが身じろぎするのを感じた。それは身をかがめると、さなえの手の上にその手を重ね、慰撫する様にさすった」。
田舎という空間。母と息子という関係。そして、祈り。最終場面へと物語が集約していくさまは圧巻。純文学の極地がここにあるといっても決して過言ではないだろう。そのくらい心を揺さぶらされる作品。
文=アサトーミナミ
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150215-00006051-davinci-life