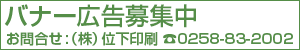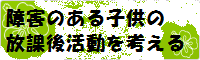国内唯一の民俗学に関する総合博物館として知られる国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)。開館30年を迎えた同館で、常設の民俗展示室が今春、全面リニューアルを果たした。その展示内容からは、約30年間で民俗学研究が遂げた変化が浮かび上がってくる。(磨井慎吾)
◆おせち料理も展示
展示室に入るとすぐ、まばゆいショーケース内に収められた現代おせち料理の数々に意表を突かれる。10万円以上する高級宅配おせち、洋風おせち、中華おせち…。デパートの売り場に並ぶおせちを再現した、民俗学の博物館とは思えない、きらびやかな空間だ。
「驚く人もいるかもしれないが、奇をてらったわけではなく、今の研究の関心が集中している領域を示すため」。展示を担当した同館の小池淳一教授は、最初におせち料理など行事食の変遷を示すコーナーを設置した意図をこう明かす。
伝統的存在だと思われているおせち料理も、実は時代に合わせて大きく変わっている。もともと家庭や地域で作っていたものが、既製品をデパートやスーパーマーケットで買って食べる消費活動に変化してきた。民俗学の研究対象は、伝統的な農漁村の生活に限定されるわけではない。商品経済の中にある現代のわれわれの日常生活も「民俗」であるとのメッセージだ。
◆同時代への取り組み
「従来の第1次産業中心の研究から、第2次、3次産業に視点が移ってきた。民俗の商品化や流通、観光化という側面にも光が当てられている」と、小池教授は話す。すぐ隣には、全国の土産物を集めた展示も。各種ご当地キャラからアニメ系イラストの“萌え土産”まで、民俗イメージがさまざまな形で商品化されている例を示す。また、マニュアル化が進む子育てのあり方や、食品や化粧品などの商品の変遷を通じてわれわれの身体観の移り変わりを示すコーナーもある。従来の海、山、里の伝統的生活についての展示は残しつつ、同時代への取り組みを示すという問題意識が強く感じられる。
展示に携わった同館の川村清志准教授は「民俗学の研究対象を指す言葉としてよく言われるのが『直近の過去』。自分の生活感覚の延長線上から出発して、この国の文化のかつての形や、現在進行形の変化を考えてもらえれば」と語る。
◆柳田国男を超えて
同館に民俗展示室がオープンしたのは昭和60年。日本民俗学の父、柳田国男(1875~1962年)が打ち立てた稲作中心の民俗学を、漁労や畑作などの世界を対置することでいかに相対化するかが旧展示設計時の課題だった。
民俗学は平成に入って以降、主な調査対象だった農林漁業の衰退などで「斜陽学問」との痛烈な批判を受けてきた経緯がある。現代社会を扱うのに加え、アイヌ文化の紹介や国境を超えた東アジア各地との相互影響なども打ち出した同館の展示は、民俗学の領域が時間的にも空間的にも拡大していることを示している。それは、民俗学斜陽論に対する一つの返答でもあるのだろう。
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/trend/snk20130502504.html