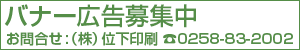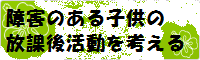動作が緩慢になり、手の震えや歩行障害などが起こる「パーキンソン病」。根本的に治す治療法はないが、症状を長く抑える薬が次々と登場し、状態に応じた薬の使い分けが可能になってきた。
パーキンソン病は50歳代の発症が多く、患者数は約14万人に上る。手足が震える、手足を曲げにくくなる、動作が鈍くなる、姿勢が悪く倒れやすくなる、などの特徴的な運動症状が表れる。
進行すると、寝付きの悪さなどの睡眠障害、夜間頻尿などの自律神経症状、幻視やうつなどの精神症状、記憶力低下などの認知機能障害が表れることもある。
脳の「黒質」と呼ばれる部分の神経細胞が減り、運動の指令を伝える化学物質「ドーパミン」を十分作れなくなることが原因と考えられている。
治療はドーパミンを補充する薬「L―ドーパ」が主に使われる。この薬の効果は高く、運動症状が劇的に改善するが、何年か使うと効果の持続時間が短くなってくる。
しかし、服用頻度を増やすと自分の意思とは関係なく四肢などが動く副作用「ジスキネジア」が起こりやすく、増量には限界がある。そこで、ドーパミンの働きを補う別の薬「ドーパミンアゴニスト製剤」を併用することになるが、効果は長時間続かず、1日に何度も効果切れが繰り返されるようになる。
全国パーキンソン病友の会が患者約1500人に行った調査では、日中に薬の効果切れで困っている患者は68%に上り、夜間や早朝にも54%が効果切れに苦しんでいた。夜間に薬の効果が切れると、寝返りを打てず目覚めたり、トイレに間に合わなくなったりする。このような状態が続くと夜間の介助が必要になり、家族の負担も増す。
そこで開発されたのが、1日1回の服用で効果が続く徐放性のドーパミンアゴニスト製剤だ。2011年以降、飲み薬タイプの「ミラペックスLA」と「レキップCR」が発売された。また今年2月には、皮膚に貼るタイプの「ニュープロパッチ」が使えるようになった。
福岡大病院神経内科教授の坪井義夫さんは「貼り薬は消化管からの吸収の影響を受けず、安定した効果を得やすい。皮膚のかぶれなどの心配がある患者は飲み薬の方がよい」と話す。
また、緊急時に約1時間の持続効果が得られる自己注射剤「アポカイン」や、L―ドーパと併用する非ドーパミン系の薬「ノウリアスト」も発売された。
パーキンソン病の治療では、脳の一部に電気を流し、症状を防ぐ脳深部刺激装置の埋め込み手術も注目されている。だが手術の対象は、L―ドーパがよく効くものの、すぐに効果が切れたり副作用がひどかったりする患者に限られる。L―ドーパが効かない患者は手術の効果も期待できず、対象にはならない。
坪井さんは「パーキンソン病の治療は薬をうまく使い分けることが重要です。治療期間が長くなる若い患者は、まずドーパミンアゴニストだけで治療を行い、劇的に効くが次第に効果が落ちるL―ドーパの使用をできるだけ遅らせるなどの工夫が必要です」と話す。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130615-00010000-yomidr-hlth