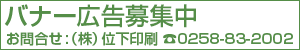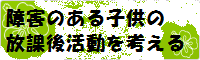江戸時代、嘉永年間(1948~1854)以前には少なくとも豚肉が公然と売られることはなかった、といわれている。
なにしろ、獣肉を口にすることが仏教によってタブーとされ、それが千年以上も続いていたわが国のことだから、豚肉に限らず、牛、馬、鹿、イノシシなど獣肉をたべることは、体だけではなく、魂までけがれるものとして人前では決して口にできないことだった。
ただし、うまいものは命をかけてでも食べるというのが人間の通性である。江戸も終わりに近くなると、その表向き口にできない獣肉を堂々と売る店が現れた。
ただし、いまのように、牛肉屋とか豚肉屋など、そのものズバリの店名を乗せるわけにはいかないから、そこはそれ、頭のいい男がいて「ももんじ屋」と称したが、“ももんじ”とは、すなわち“お化け”──そこで川柳子が、「きのうまでばかしたやつを麺町」と冷ややかした。
麺町は、江戸時代、ヤミの獣肉屋街として有名だったところで、今のすましたオフィス街からはとても想像できない街だったのである。
ところで、そうした江戸時代でも、どうしても食べる気になれなかったのが豚肉らしく、川柳子も「大いびきかきながら豚あるいている」と、いまのわれわれから見ると、首をかしげたくなるような句を残している。しかし、幕末になると、オランダ医学が普及したこともあって、とくに研究熱心な医者のなかには豚を飼う者があったらしい。
もちろん、解剖研究のためだが、川柳子はここでも、また、「外科殿の豚は死に身で飼われている」「豚殿のいるところと外科殿を教え」「かねてなき身と思ってる」と冷やかしている。もっとも、長崎や鹿児島ではいちはやく豚肉が食べられていたから、「よかものさなどと壺からはさみ出し」などとあり──これは、豚骨料理か、でなければ豚の角煮であろうと、想像される。
[ カテゴリー:食の安全 ]
豚肉と川柳
団体理念 │ 活動展開 │ 団体構成 │ 定款 │ プライバシーの考え方 │ セキュリティについて │ 事業 │ メディア掲載 │ 関連サイト │ お問い合わせ
copyright © JMJP HOT TOWN Infomaition Inc. All Rights Reserved. NPO法人 住民安全ネットワークジャパン
〒940-0082 新潟県長岡市千歳1-3-85 長岡防災シビックコア内 ながおか市民防災センター2F TEL:0258-39-1656 FAX:020-4662-2013 Email:info@jmjp.jp