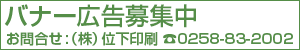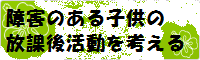生まれつき重い心臓の病気を持った新生児が手術で救われるようになった。画像診断など医療技術の進歩により胎児段階で病気が判明し、出産前から医療チームを組み、効率的に手術できる体制が取られるようになったからだ。一方で、小児のときに手術した患者が成人になって再び心臓病で入院するケースが増加。医療関係者は「成人になっても定期的に通院し、経過を見守ることが不可欠」と指摘する。(坂口至徳)
◆各科が連携
先天性の心臓病を持つ新生児は100人に1人で、日本では毎年約1万人が出生すると予測され、その約50%は外科手術などの治療が必要だ。国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)の小児循環器・周産期部門は、生まれつき重い心臓病を持つケースを積極的に受け入れている。手遅れにならないように胎児のときから母親とともに入院し、診療を行うケースは5割超という。
近畿圏在住のA子さんは妊娠後期の超音波検査で、胎児が重症の心臓病である可能性が示唆された。このため、同センター周産期科で、小児循環器科の医師らと合同での診療がスタートした。
詳細に超音波検査を行ったところ、赤ちゃんの心臓の筋肉に栄養を送る冠動脈(通常直径2ミリ程度)が直径1センチ以上に膨らんでいるうえ、右心室に直結していた。この状態では、出生後に肺呼吸が始まって右心室の血圧が下がると、ほとんどの血液が右心室に流れ込み、心臓の筋肉に届かずに重篤な筋肉の障害を起こす。
そこで、周産期科と小児科が厳重に管理して出産し、出生直後には小児科と心臓外科が超音波検査で赤ちゃんの心臓の異常を詳細に確認。1時間以内に緊急手術を始め、冠動脈が右心室と直結した部分を縛ったところ、心臓の筋肉への血流が回復した。手術は成功し、2カ月後には退院。現在は一人歩きもできるようになった。
同センターの白石公・小児循環器部長は「胎児期から心臓病を診断し、最も負担が少なく一生の生活の質が保障できる手術の時期や治療法について、関連各科が連携して協議している」と説明する。
◆成人で新たな症状
このような診療が成果を上げている背景には、心臓の超音波検査やCT(コンピューター断層撮影装置)など画像診断の技術の発達がある。これによって、胎児の段階で「心臓から出ていく血管の配置が逆」「2つある心室の一方が極端に小さい」など重篤な症状を起こす異常を見つけやすくなった。
ただ、一方で、小児期になされた先天性心臓病の手術で治ったとされる人が、成人になって不整脈や心不全などの症状が新たに出るケースが増えている。成人に達した先天性疾患の患者は40万人を超え、既に未成年の患者数を上回る。成人患者のうち入院が必要となる可能性のある人が3分の1を占める。白石部長は「生まれつきの小児の心臓病の治療は歴史が浅く、手術後の長期間のデータが少なく、予測がつきにくい。思春期に自覚症状がなくなり、根治したと勘違いして通院しなくなるケースなども多い」と指摘する。
新たな症状は加齢の影響が出る30代以降に起きるとみられ、同センターでは「成人先天性心疾患外来」を設け、継続した治療にあたっている。
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/life/medical/snk20130220513.html