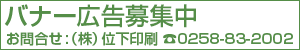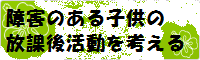東日本大震災に加え、東京電力福島第1原発事故に見舞われた福島県。第1原発が立地する大熊町や双葉町は全町避難を余儀なくされた。事故からもうすぐ半年。古里を奪われた人々の望郷の思いは募る。
◇全町避難の大熊・双葉--慣れぬ土地で半年
背丈ほどの雑草に覆われた庭。倒れた家具。食器が散乱したキッチン--。「これが本当に俺の家なのか……」。今月1日の一時帰宅で半年ぶりに戻った我が家は、変わり果てていた。
大熊町夫沢の佐藤洋一さん(62)の自宅は、第1原発の南2.5キロにある。妻道子さん(62)と73年に結婚。富岡町から道子さんの故郷に移り住んだ。
89年に運送と産業廃棄物処理の会社を設立し、自宅も建てた。長男洋道さん(37)ら3人の子も会社を手伝ってくれるようになり、徐々に仕事の規模が拡大した。97年には約3億円を投じ、自宅近くに産廃処理用焼却炉も造った。「家族みんな、いつも一緒でね。そりゃあ幸せでしたよ」
穏やかな暮らしを、原発事故が一瞬にして奪った。一家は隣の田村市や新潟県新発田市など5カ所の避難所を転々とした後、洋一さんと道子さんらは喜多方市内のアパートに身を寄せた。長女とみえさん(28)は新潟市に移った。「賠償はいらないから震災前の生活に戻して」。離散した家族を案じ、道子さんは涙に暮れる。
8月27日。福島県を訪れた菅直人前首相が、原発周辺には長期間戻れない可能性に言及した。「国のトップに言われると、ずしーんときたね」。洋一さんの絶望感は深まった。
会社経営者としての責任もある。従業員22人のうち、15人が避難先などで会社の再開を待つ。運送業だけでも始められないかと思案するが、喜多方市周辺には縁もゆかりもない。「すぐにはうまくいかねえべ」。洋一さんはため息をついた。
洋道さんは、喜多方市に妻と幼い3人の子を残し、仕事のため約120キロ離れた北茨城市で、単身で暮らす。「パパおんぶして」。毎週末に帰宅すると、子供が競うように飛びついてくる。
もうすぐ2歳の長男洋仁君は、半年続く避難生活の間に「パパ」と言えるようになった。子供の成長が支えだが、妻豊香里(ゆかり)さん(38)は「何も解決しないまま半年たっちゃった」と、好転しない事態に焦りも感じる。
洋道さんも父の家に隣接する自宅に今月1日、一時帰宅した。家をカメラで撮影し、家族に見せた。お気に入りのぬいぐるみや旅行先で描いてもらった家族の似顔絵。次女明莉(あかり)ちゃん(7)は食い入るように写真を見つめ、「戻りたい」と涙を流した。長女光莉(ひかり)ちゃん(9)は気持ちを押し殺すように黙り込んだ。「子供たちは負の遺産と何十年も向き合わないといけない」
知人には「もう帰らない」と決めた人も出てきた。それでも洋道さんは言う。「どこにいても心は故郷にある。何十年もたって、自分の腰が曲がりつえをついていたとしても、子供や孫のために地域に戻って復興したい」【福永方人、銭場裕司】
◇何を目標にすれば…
埼玉県加須市の旧騎西高校に双葉町から避難している土田光雄さん(71)の自宅は、第1原発から約3.5キロ。腕のいい大工として評判だった。
一時帰宅した7月下旬。自分が建てた近所の家が倒れずにいるのを見て、うれしさがこみ上げた。「自分の家と思って建てたんだから」。43年間、仕事一筋だった人生の証しのような気がした。
雑草に囲まれた自宅は線量が高い。「もう帰れないかもしれない」。危惧していたことを、現実として受け止めざるを得なかった。双葉町で築いた信用も、加須市では通用せず、大工はあきらめるしかないと考えるように。「何を目標にすればいいのか」と自問する日々が続く。
避難所では妻(69)と長男(44)と一緒に暮らす。一時帰宅で持ち帰った趣味の尺八。他の避難者の迷惑にならないように、校舎の陰で吹くのが楽しみだ。「すべてがパーになった」。吹いている間だけ悔しさが少し和らぐ。【藤沢美由紀】
◇避難勧奨の伊達・ホットスポットの福島--線量計と半年
放射性物質が子供の健康や農作物に影響を及ぼさないのか。地元で生きることを決めた人々の戸惑いは続く。
「いつ死んでもいいくらいには生きたから」。伊達市霊山町(りょうぜんまち)上小国の本組集落に住む農業、高橋芳次さん(76)は力なく笑った。
集落28世帯のうち高橋さん方を含む20世帯が「特定避難勧奨地点」に指定され、避難を促された。同居の長男家族は、7月末に約15キロ離れた市営住宅に転居したが、高橋さんは、夫婦2人で残ることを決めた。
早朝、目覚めると畑に出る生活を60年以上続けてきた。被ばくや作物の出荷制限の不安はあるが、土から離れることは自分の生活を壊してしまうような気がする。長男は「一緒に暮らそう」と言ってくれるが、毎日田畑に通うための乗用車のガソリン代などが家計を圧迫すると思うと、あきらめざるを得ない。
集落で家族全員が避難したのは3世帯。残り17世帯のほとんどが高齢者で、生活の変化を嫌った。「先が長い人生でねえからな」。近所の住民と顔を合わせるたび、そんな話になる。
初秋の風が吹き始めた9月上旬の昼下がり。収穫したサヤインゲンを農作業小屋で選別する高橋さんの胸元には、市から支給された線量計「ガラスバッジ」が。数字が表示されないタイプで、定期的に市が回収して積算線量を知らされる。「なんだか俺たち、実験台みたいだ」。高橋さんはつぶやいた。
8月の日差しが降り注ぐ福島市渡利の保育園。プールに子供たちのはしゃぎ声が響く。水が入った約1400本のペットボトルがプールサイド一面に並ぶ。「地表からの放射線を遮蔽(しゃへい)するらしい」という情報に、確かな科学的裏付けはなかったが、園も保護者も期待した。
線量が局地的に高くなる「ホットスポット」があるとされる同地区。学童指導員の佐藤秀樹さん(44)は、妻晃子さん(39)と子供3人の計5人で暮らす。末っ子で長女の真仲ちゃん(2)が通うこの保育園でも事故後、園庭で最高毎時5マイクロシーベルト超を観測した。妻子は3月下旬、岩手県奥州市の実家に避難した。新年度を迎え、渡利に住み続けるかどうかの選択を迫られた。
「避難先では仕事がない」「子供の体が心配」--。夫婦で堂々巡りの話し合いが続き、声を荒らげたことも。学童保育に通ってくる子供の顔を思い浮かべると、地域を離れる気にはなれなかった。晃子さんも事務職の仕事にやりがいを感じている。「自分たちで線量を下げる努力をするしかない」。渡利で暮らし続けようと決めた。
「渡利は大丈夫?」。親戚や知人に何度も尋ねられる。そのたびに、この選択が正しかったかどうか、心が揺れる。「安全だよ」とは答えられないが、「今は家族が一緒にいることが一番大切」と自分に言い聞かせる。
園庭の線量は、毎時0.4~0.8マイクロシーベルトに下がったが、園の判断で外で遊ばせてはいない。10月の運動会は実現させてあげたい。佐藤さんは言う。「子供がのびのび過ごせる環境を早く作りたい。不安はあっても、ここで暮らしていくのだから」