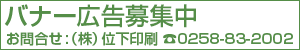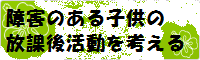●「遠藤諭の『コンテンツ消費とデジタル』論」とは?
アスキー総合研究所所長の遠藤諭氏が、コンテンツ消費とデジタルについてお届けします。本やディスクなど、中身とパッケージが不可分の時代と異なり、ネット時代にはコンテンツは物理的な重さを持たない「0(ゼロ)グラム」なのです。
本記事は、アスキー総合研究所の所長コラム「0(ゼロ)グラムへようこそ」にて2010年10月15日に掲載されたものです(データなどは掲載時の数値)。遠藤氏の最新コラムはアスキー総合研究所で読むことができます。
19世紀後半に、ミシンやタイプライターや電話が登場し、20世紀初頭にラジオや飛行機、特殊相対性理論などが出てきて、世界はどんどん近代化していった。それと同じ時期に、ヨーロッパでは前衛的な芸術運動が盛んになり、表現の世界は混沌の中に向かっていった。
エジソンがキネトスコープを発明したのは、1891年。映画を実用化したといえるリュミエール兄弟は、「活動写真」という名前のとおり、世界の風景を撮影するのに使った。それから20年以上もかかって、『戦艦ポチョムキン』(1925年)でモンタージュ手法(複数のカットを編集して見せる技法)が確立されて、映画は我々の知っているような映画となったともいえる。
ネット時代のネイティブなコンテンツの進化にも、これからまだ長い道のりがあるとしか思えない。テクノロジーと芸術や作品の世界は、深くリンクしているからだ(たとえ表現の手段が新しいテクノロジーを直接使っていなくてもである)。
2010年10月14日から17日まで、日本科学未来館、東京国際交流館で「デジタルコンテンツ EXPO 2010」が開催された。グラフィックス表現や表示デバイスが劇的に変化している今、まさにデジタルコンテンツは大きな曲がり角に来ているといえる。その中で、主催者プログラムのシンポジウム『擬人化ジャパン ~日本発・擬人化キャラクタがモノづくりを語る~』に参加させてもらった。
「擬人化」とは、もちろん国語の時間に教えられた「擬人化」の意味だが、アキバ的な意味で独特の盛り上がりを今見せている。例えば、小惑星探査機「はやぶさ」の擬人化。「はやぶさ」が「はやぶさたん」という女の子に擬人化して、地球から往復60億kmも“お使い”に行ってくるのである。
なんでも擬人化できるのだが、一般には、共有感があり、身近に感じるものであることが多い。そうすることで、まったくオリジナルなものを素材に語るよりも受け入れられやすくなる。受け手にも、知っているものが萌え化してどんなキャラクターになるかという楽しみがあるからだ。
そして昨今の擬人化では、題材がコンテンツではなくモノであるころに新しさがある。そこに、日本のオリジナリティとか、ドメスティックな感覚というものが作用してくる。擬人化は、モノ作りにとって大切な何かに触れているのかもしれない。今の萌え系の人たちのセンスを感じとっているくらいでないと、次の時代の製品やサービスを生み出せないのではないかとも思える。
『戦艦ポチョムキン』で映像を切り刻んで編集し、つなぎあわせて表現したことが、当時は新しかった(今では当たり前に受け入れているわけだが)。同様に、今はまったく思いもよらないようなことが、デジタルコンテンツの行く先だったり、デジタル機器の役割になるかもしれないのだ。
●特徴的な世代分布から「萌え」を分析してみる
「擬人化」は、「萌え」の文脈で見ることができる(デジタルコンテンツ EXPOのパネルディスカッションで座長を務められた、京都工芸繊維大学大学院倉本到準教授も指摘している)。例えば、秋葉原のデジタル&コンテンツ系ショップ三月兎の店頭などを参考に、「擬人化」のタントラ図を書くとすると、次のようなものになる。
●けいおん!やメイドカフェに萌えているのは誰か
それでは、今、誰がどう萌えているのか? ネット行動やコンテンツ消費に関するアスキー総研の1万人調査『MCS(メディア&コンテンツサーベイ)2010』で調べると、「萌え」に関する特徴的な構図が見えてくる。
例えば、MCSで「本や雑誌記事の興味テーマ」として、「萌え」と答えた人を性年代別で集計してみる。
なんといっても、20代が「萌え」が興味テーマと答えた人のピークとなっている。我々の他のデータでも明確に出ているが、今の若年層はとてもアキバっぽい。そして、もうひとつ目に付くのが、30代の減少が大きいのに対して、40代がしぶとく萌えていることだ。グラフを見ると、男性40代のところが腰骨のように張り出している。
実は、「萌え」に関係するコンテンツの視聴層やサービスの利用層を性年代別で集計すると、ほとんどの場合これに似たカーブにお目にかかることになる。例えば、「萌え」系の人がもっとも見ているテレビ番組の1つ、『けいおん!』を見てみよう。
メイド喫茶の利用者やコミケ(コミックマーケット)参加者など、「萌え」に関係するサービスでも、この特徴的なカーブになる。
●auユーザーは「萌え」ている?
単純に、20代のコンテンツの消費量が多いということだけでは説明できない。「萌え」でない興味テーマでは、このようなカーブにならないからだ。
これ以外にも、「萌え」系の人たちの特徴を示すデータはある。例えば、「萌え」の人の使用ケータイは、ドコモが38%、auが36%、ソフトバンクが26%となる。全体では、同46%、31%、24%のシェア(ネットを利用する12~69歳男女)なので、auを使っている比率がかなり高いことが分かる。ケータイ業界では「auはアニメファンに強い」といわれてきたが、それ以上の数値を示している。
しかし、興味深いのは20代が萌えていて、40代もしぶとく萌えているという性年代別のデータではないかと思う。これについては、いずれジックリ触れることにしよう。
●カワイイと「萌え」では、視線位置が異なっている
私が、「萌え」という言葉に初めて接したのは、編集長をやっていた『月刊アスキー』に連載された「桃井はるこ新聞」(1998~2001年)においてだった。バックナンバーを引っ張り出してみると何度か出てくるが、彼女の周辺ではもっと頻繁に普段から使われていた。
ここ数年のトピックの1つは、『萌える英単語 ~もえたん~』(三才ブックス刊)のように「萌え」がスタイルとして成立したことだろう。「萌え萌え」→「萌え」となり、「工場萌え」のように一見当たり前でないものにも萌えるというのが楽しい。
1980年代の後半、日本の女子大生たちは「カワイイ」という言葉を濫用していた。「カワイイ(可愛い)」の意味は時代とともに大きく変化してきたわけだが、ここでは、自分の価値基準を商品などに対してマーキングするために使われた「カワイイ」をいう。
この「カワイイ」は、バブル期をはさんで、そう呼ぶものを異質化させる呪文のような効果をもつほどになり、それが今日の「キモカワ」まで通じている。そのようにして、濫用、記号化、俗化した「カワイイ」に対して、より純化した新基準が「萌え」だった。
ここで重要なのは、「カワイイ」が女子専用の言葉だったのに対して、「萌え」は、男の子も堂々と使うことができる言葉だったことである。
そしてもうひとつ、「萌え」において、それがいかに真摯なものであるかを示すことも起きている。「カワイイ」というときの視線のベクトルは伏角(ふかく)なのだ。小さいモノに対して向けられるものだからというのもあるが、メンタルな部分でも視線が降りていっている。それに対して、「萌え」というときのベクトルは、やや上向きな仰角になっていると思う。
このことと、「萌え」文化の中で起きている「擬人化」という表現様式とは、無関係ではないように思える。
ところで、ここに書いているようなことを、先日Twitterでつぶやいていたら、@o_obさん(ConTEXと国際3Dフェア委員の白井暁彦氏)から以下のようなツイートをいただいた。
そうなのだ、擬人化というときにはその「萌え」のパワーが、モノ作りとピュアに関わってくる。YouTubeとかアップルとかFacebookとか、いつもそれで決まりという答えはなくて、テクノロジーだけは絶えず前に進んでいく。今、目の前に見えているものを超えたところにモノ作りの本質があるのではないか?
映画における『戦艦ポチョムキン』のような、ネット・ネイティブのメディアの形は、あるとき誰かの手の中から、ひょっこりと出てくるはずのものなのである。 【遠藤諭、アスキー総合研究所】
●遠藤 諭(えんどう さとし)
1956年、新潟県長岡市生まれ。株式会社アスキー・メディアワークス アスキー総合研究所 所長。1985年アスキー入社、1990年『月刊アスキー』編集長、同誌編集人などを経て、2008年より現職。著書に、『ソーシャルネイティブの時代』、『日本人がコンピュータを作った! 』、ITが経済に与える影響について述べた『ジェネラルパーパス・テクノロジー』(野口悠紀雄氏との共著)など。各種の委員、審査員も務めるほか、2008年4月より東京MXテレビ「東京ITニュース」にコメンテーターとして出演中。
コンピュータ業界で長く仕事をしているが、ミリオンセラーとなった『マーフィーの法則』の編集を手がけるなど、カルチャー全般に向けた視野を持つ。アスキー入社前の1982年には、『東京おとなクラブ』を創刊。岡崎京子、吾妻ひでお、中森明夫、石丸元章、米澤嘉博の各氏が参加、執筆している。「おたく」という言葉は、1983年頃に、東京おとなクラブの内部で使われ始めたものである。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110608-00000022-zdn_mkt-ind