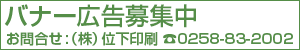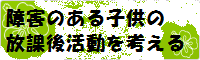東日本大震災後、被災地では日々変化する生活情報が欠かせず、地域に密着した地元紙の役割は大きい。岩手県大船渡市の「東海新報」の記者、鈴木英里さん(31)は、津波で自宅を失いながらも「かけがえのない故郷に、自分より困っている人が大勢いる」とペンを走らせ続けている。
■津波が持ってった
3月11日。午前中に街の話題などを取材した鈴木さんは、会社に上がって午後に原稿を書き終えたちょうどその時、震度6弱の激しい揺れに見舞われた。
「これは津波が来る。写真を撮りに行かなければ」。社員の念頭にあったのは、つい2日前の3月9日にあった津波だった。漁業被害は大きかったものの、陸地にまで被害はなかった。「今思えば甘い気持ちだった」と鈴木さん。
同市三陸町越喜来(おきらい)へ向かう途中、顔見知りの高齢者や介護職員らを荷台に乗せた軽トラックが通りかかった。皆、顔面蒼白。「何があったんですか。建物はどうですか」と呼びかけると、「流れてます!」の一言が返ってきた。
その言葉の意味がよく理解できないまま、車で峠を下った鈴木さんの目に、木立の間から信じられない光景が飛び込んできた。
「見慣れた風景は跡形もなかった。すべてがなくなっていた。津波だと頭では分かったが、とてものみ込めなかった」
車を降り、高台で立ちつくす中年の女性に「これ、津波ですか」と聞くと、女性は「持ってった。全部、津波が」と言ったきり、泣き崩れてしまった。
被害を記録しようと、夢中でシャッターを切った。ただ、呆然とした人々の表情は撮れなかった。「私も地域の人間で、自分が撮られたら嫌だろうと思うと、どうしてもはばかられて」
携帯電話は通じず、会社への道路は流出物の山で寸断。写真を社に届けることができない。鈴木さんは帰社を諦めた。
「会社では私、死んだと思われてるかもしれないな…」
そのころ会社では、自家発電を頼りに、社に戻れた社員らが号外を編集していた。2千部をカラーコピーで印刷し、翌朝、社員が手分けして避難所などに運んだ。
■見出しに「希望」を
鈴木さんは翌12日に出社できた。任された仕事は、写真を大きくレイアウトするグラフ面の編集だった。
「爪痕無残…各地で深刻被害」。鈴木さんがこの日つけた見出しだ。
4日後、17日付のグラフ面では、一転してこんな見出しを添えた。「“私たちは負けない”『生き抜こう』懸命の被災者ら」
鈴木さんは「報道が被災者の心に塩を塗ることになっていないか。せめて見出しだけでも希望を」と、心境の変化があったと話す。
同社では、社員が避難所を分担し、掲示された避難者リストを撮影しては会社に戻り、片端から記事に打ち込む膨大な作業を続けた。ほかにも、身元不明遺体情報、生活情報、避難所の状況などを連日、綿密に記事化してきた。
「地元紙だから、どこに行っても取材したことのある方や、その知り合いばかり。生きていてくれたのがうれしく、私のことも『無事だったの』と喜んでくれる。取材に私情が入るのがいいのかは分からないけれど、自然と明るい記事を書きたくなる」と鈴木さん。
卒業式で元気な表情の子供たち。無事出産した女性。市街地から離れた公民館でも協力し合って避難生活を送る人々…。記者の温かい気持ちは紙面に反映されていった。
■涙で見えなくなる
鈴木さんの自宅も津波にのまれた。「私より困っている人がはるかに多い。つらいという気持ちはない。今こそ記者の役割を果たすときだと感じている」。そう話す一方、「毎日涙で前が見えなくなる。仕事中に泣くなんて社会人失格。でも、悲しくて泣くこともあるけれど、うれしくて泣ける方が多い」とも。
東海新報は4月1日から順次戸別配達を再開している。地域に溶け込み、生活を支える地元紙。「そのことは、これまで頭では分かっていたつもりだった。でも、3月11日を境に、実感として初めて胸にストンと落ちた」と鈴木さんは語った。