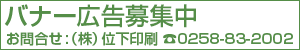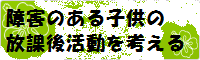日本人を直撃する「人口急減」の切実すぎる未来 出生数90万人割れの衝撃から何が見えるか
日本の人口減少が大きな問題になっている。その背景にあるのが「出生数」の低下だ。出産期の女性人口が減少し、さらに1人の女性が生涯に産む子どもの数も大きく減少を続けている。
そんな中で、2019年の出生数が90万人を割る可能性が高くなったと報道された。2016年に100万人の大台を下回ってから、わずか3年で90万人を割る事態となっている。
とはいえ、人口減少につながる出生数の低下は、その原因がまだはっきりしていない。近年は日本だけでなく韓国や香港、シンガポール、台湾、タイといったアジア諸国でも、女性が生涯に産む子どもの数を示した「合計特殊出生率」が日本以上に低くなる現象が起きている。
イタリアなどの先進国でも、共通の悩みとして認識されており、2018年には人口の増加を続けてきたアメリカでも出生率の低さが問題になった。
なぜ、女性は子どもを産まなくなってしまったのか――。
フランスのように出生数を伸ばした国もあるから、一概に「豊かになったから」という個人の問題だけでは説明がつかない。そんな中で、日本の人口減少はいまや待ったなしの状態。世界共通の悩みにもなってきた出生率の低下を考えていこう。
団塊ジュニアの出産期がほぼ終了
今回、報道された出生数90万人割れの情報は、厚生労働省が発表している人口動態統計の速報値による予測報道だが、今年1〜7月の出生数は前年同期比5.9%減の51万8590人になったことに基づいている。
5.9%の減少は30年ぶりの減少ペースであり、その背景には「団塊ジュニア」世代が40代後半となり、出産期の女性人口が大きく減少したことが原因と指摘されている。
団塊ジュニアとは、戦後すぐに生まれた1947年から49年までの「団塊世代」の子どもたちを示す言葉だ。狭義には1971年から1974年の3年間に生まれた世代で、第2次ベビーブーム世代とも言われる。ピークとなった1973年には年間で210万人が誕生している。
団塊世代のピークとなった1949年には270万人が生まれており、そこまで到達しなかったものの、団塊ジュニアの存在は大きな注目を集めた。団塊世代のように、新しい価値観や消費を創出してくれる世代になるのではないかと期待されたのだ。
ちなみに、広い意味では1970年代に生まれた人を総称して団塊ジュニアと呼ぶ場合もあり、就職氷河期世代の一角を担っているという捉え方もある。
その団塊ジュニアのトップランナーである1971年生まれも、2019年には48歳。1974年生まれの団塊ジュニア最後の世代も45歳。一般的には、40代前半までが出産適齢期と言われている。以前から、団塊ジュニアがそれを過ぎた後の人口減少が心配されていたが、ここに来ていよいよ出生数の減少という形になって表れたと言える。
第3次ベビーブームは幻に終わった
日本の合計特殊出生率は、2005年の1.26人を最低に少しずつ改善され、3年前には1.45人にまで上昇。その原動力となったのは団塊ジュニアとされている。しかし、ピーク後の3年間は下落を続けており2018年には1.42人にまで下落した。
実際のところ、団塊ジュニア後の出産適齢期を迎える女性人口は大きく減少している(2018年10月1日、人口推計より)。
●40歳代 …… 907万人
●30歳代 …… 696万人
●20歳代 …… 578万人
出生数が100万人を割ったのは2016年。厚生労働省の推計では、その後2021年に90万人を割り込むとみていた。それが2年前倒しで90万人割れしたわけだ。日本の人口減少に拍車がかかるのは避けられない状況と言っていい。
期待された第3次ベビーブームは、産業界や広告代理店、メディアなどが期待してさまざまなイベントやキャンペーンを仕掛けたものの、空振りに終わったことは周知のとおりだ。
バブル崩壊後の失われた20年に差し掛かり、20代の結婚適齢期にいた団塊ジュニアは、経済的な問題から「結婚できない」「結婚しても子どもをつくらない」もしくは「産んでも1人」と言った状況となり、第3次ベビーブームは幻となってしまった。
この幻と終わった第3次ベビーブームが、現在の日本の少子化の最大の要因であると分析する人も多い。
失われた20年の中で、非正規雇用者が増えたために「晩婚化」をまねいた。晩婚化はやがて女性が子どもを産む年齢を押し上げる。「晩産化」を進行させ、第2子、第3子を産む機会が減少。少子化に拍車がかかってしまったわけだ。
実際に、第1子を産んだときの母親の年齢は30.7歳(2018年)となっており、ここ数年過去最高水準を更新している。
団塊ジュニア世代の次は「就職氷河期世代」
原因はともあれ、日本の出生数が年々減少しており、日本に構造的な問題点をもたらしたと言える。例えば、少子化と並んで高齢化が進み、賦課方式で維持されてきた公的年金制度の維持運営が疑問視されている。
厚生労働省のパンフレットでもよく見かける「高齢者を支える現役世代」がどんどん減少していく状況だ。もっとも、現役世代の数が減少していくのは、これからが本番で、安倍政権が現在取り組んでいる「全世代型社会福祉」は、まさに少子化への対応と言っていいだろう。
この10月1日からは、幼稚園や保育園にかかる費用を無償化する「幼児教育・保育の無償化」がスタートした。住民税非課税の世帯が対象だが、認可外保育園やベビーシッターの費用にも、一定の補助金が出ることになった。この制度が機能して出生数が上がるかどうかは、結論が出るまで待たなくてはならない。
さらに、遅まきながら就職氷河期世代に対するサポートを開始したのも少子化対策の一環だ。内閣府が毎年まとめている『少子化社会対策白書』の令和元年版によると、「どのような状況になれば結婚すると思うか」という問いに対して、次のような回答になっている(複数回答)。
1. 経済的に余裕ができること …… 42.4%
2. 異性と巡り合う(出会う)機会があること …… 36.1%
3. 精神的に余裕ができること …… 30.6%
4. 希望の条件を満たす相手に巡り会うこと …… 30.5%
5. 結婚の必要性を感じること …… 28.4%
経済的に余裕ができることが結婚できる最大の要因というわけだ。言い換えれば結婚できるだけの経済力がないことを意味している。ちなみに、「結婚後も働くかどうか」という問いに対しては、60%以上が結婚後「夫婦ともに働こうと思う」と考えており、その理由が「経済的に共働きをする必要があるから(57.8%)」と答えている。
結婚できたとしても、経済的には共働きを強いられる、と考えている人が多いということだ。
団塊ジュニアに次ぐ年齢層は、現在40代前半もしくは30代後半になるわけだが、この世代はいわゆる「就職氷河期世代」「ロストジェネレーション世代」と呼ばれる人たちだ。大学や高校を卒業したときの「有効求人倍率」(求職者に対する求人数の比率のこと)が0.5倍を割っているような状態の中で、正社員になれずに非正規労働者として生計を立てている人が多い。
最近になって、こうした就職氷河期世代を対象にした求人が徐々に始まっているが、宝塚市が3人の募集枠で就職氷河期世代に的を絞った求人を行ったところ、1635人もの応募があったというのは有名な話だ。結婚どころではない経済状況の人が多く、仮に結婚したとしても子どもを2人、3人ともうけるような状況ではないのかもしれない。
遅きに失した感は否めないが、90万人を割った出生数を考えたとき、この就職氷河期世代の人々の生活レベル全体をいかに上げるかが、出生数減少の歯止めになるのかもしれない。
ただ、これは日本特有の事情と言える。海外にはなかった「バブル崩壊」が就職氷河期世代を誕生させたわけだが、この世代特有の問題というかたちで日本の出生数低下を説明するには無理がある。
というのも、バブル崩壊がなかった海外でも、数多くの国がここに来て少子化に悩み始めたからだ。国連がまとめた「世界人口推計2019年版」によると、世界人口の高齢化が進み、さらに人口が減少している国の数が増えていると指摘している。
あのアメリカも人口減少時代に突入?
「世界人口推計2019年版」によると、2010年以来、人口が1%以上減少している国と地域が27に及ぶそうだ。場所によっては、低い出生率に加えて移民流出率の高まりによって、人口が大きく減少している国や地域が多くなっている。
しかも、人口減少は今後さらに進むと国連は想定している。2019年から2050年にかけては、55の国と地域で人口が1%以上減少すると予想。そのうち26の国と地域では10%以上の人口減少になる可能性を指摘している。たとえば中国では、同期間で人口が3140万人、約2.2%減少すると予想している。
ちなみに、今後10年間で「移民が増えて人口減少を部分的に緩和する」ことが見込まれている国の中に、国連は日本を挙げている。日本も深刻な人口減少の波が押し寄せており、移民の受け入れによって人口減少は多少緩和されるとみているわけだ。
いずれにしても、世界はいま人口減少に直面し始めた国が目立つようになってきた。人口面では優等生だったアメリカもその1つだ。2018年の出生率が史上最低を記録したことがニュースとなり、アメリカ国内の10〜20歳代の女性の出生率は、1986年以来最低の水準になった。
もともとアメリカは、高い出生数に加えて、移民の流入などでG7の中では唯一人口が増えている国として知られていた。それがまた強い経済成長率の証とも見られていた。アメリカの合計特殊出生率は1.76人(2017年)で、 日本の1.42人よりも高いものの、フランスやイギリスよりも低くなっている。主要国の合計特殊出生率は次のとおり(2017年)。
●フランス …… 1.90人
●スウェーデン …… 1.78人
●英国 …… 1.76人
●アメリカ …… 1.76人
●ドイツ …… 1.57人
●日本 …… 1.43人
●イタリア …… 1.32人
アメリカでは、10代の若者の出生数が史上最低を記録。現在は、50代半ばから70代前半のベビーブーマー世代の子ども達が出産期を迎えており、日本同様に第3次ベビーブームとはならない状況と言われている。
アメリカの特徴は、ほかの国よりも比較的結婚年齢が早いものの若くして子どもを持ちたいと言う意識が徐々に薄れつつあるようだ。その背景にあるのが、日本同様「経済的不安定」と言われる。
アメリカは、日本以上に労働者に厳しい環境で、いつクビを切られるかわからない。育児補助金や育児休暇を取りやすい環境も整備されていない。加えて、若い世代が大学進学のための学生ローン、結婚してからの住宅ローンの返済などに追われており、借金漬けの中で出産を決心するには時間がかかり、結局「晩産化」が進んでいると言われる。
経済成長著しいアジアも少子化へ?
一方、国連の推計では世界の人口は2050年に97億人に達したあと、2100年頃に110億人で頭打ちと予想している。現在の世界人口が77億人だから、今後30年でまだ20億人増加すると予想しているわけだ。
確かに、相変わらずアフリカ諸国など経済的に疲弊している国での出生数は極めて高い。世界的な規模で見れば、人口減少よりも「人口爆発」のほうが深刻だといわれている。
地球全体では、毎日22万7000人が生まれている。世界の人口が100億人になったときに、地球温暖化や食糧不足はどうなるのか……。人口爆発は、貧困がもたらす副産物だと言われているが、発展途上国では人口爆発に悩み、先進国は少子化に悩む。そんな構図と言っていいのかもしれない。
ところが少子化は、先進国特有のものと考えられていた現象だが、ここにきて発展途上にある国、あるいは最近になって先進国のグループに入ってきた国も出生率の低さが目立ってきた。
例えば、近年経済成長著しい韓国や香港、台湾といった国も、日本以上の少子化に悩み始めている。アジア各国の合計特殊出生率(2017年)を比較すると次のようになる。
●シンガポール …… 1.16人
●韓国 …… 1.05人
●香港 …… 1.13人
●台湾 …… 1.13人
●タイ …… 1.47人
●日本 …… 1.43人(2018年)
アジア各国の合計特殊出生率が極めて低い状況にあるのは、近年の著しい経済成長の副産物なのかもしれない。日本とはまた違った意味での少子化の原因があるはずだ。この原因をきちんと抑えなければ、なぜ出生数が減り続けるのか……。正確な分析は難しい。
格差がもたらす社会不安が少子化の原因か?
問題は、日本だけではない少子化現象の原因だ。なぜ、経済成長を遂げている国々の出生率は下落し続けているのか。さまざまな国でも挙げられている要因をいくつか紹介すると……。
1. 経済的な事情によるもの(格差社会)
2. 結婚率の低下(結婚という制度に対する批判)
3. 保育園などの子育て支援の体制が未整備(教育費の高騰)
4. 晩婚化、晩産化の進行
5. 少なく生んで大切に育てる意識の浸透(少数精鋭主義)
6. 心理的な抑圧
この中で最も大きな問題は「経済的な事情によるもの」、すなわち貧困問題と言っていいかもしれない。21世紀に入って、リーマンショックを機に、世界はより激しい「格差社会」に突入した。高騰する教育費を考えると、子どもの数を減らそうと考えるのは自然なことだ。
世界で数十人の人間の富が、それ以外の99%の富と同等、もしくは上回っている現状は、大きな問題と言っていい。なぜこんな社会になったのか。一言で言えば「政治の問題」と言っていい。
富裕層におもねることで莫大な富が政治家に流れ、巨万の富を得た富裕層はますます税金を払わないで済む状況になり、それ以外の貧困層は子どもすら産めない貧困に陥りつつある。言い換えれば、巨万の富を得た富裕層は少子化の責任を取るべきであって、 きちんと利益還元するべきだ。
そしていま、クローズアップされている問題が「心理的な抑圧」という問題だ。経済的な理由による少子化は一瞬正論のように思えるが、よく考えると世界中で爆発的に人口が増えているのは、みな最貧国と呼ばれているような地域が多い。避妊に対する無知という面もあるが、貧しいことと出生率の間にはそう関係がないのかもしれない。
中国も、国民の大半が貧困から脱却したと同時に、少子化に陥っている。経済的要因というよりも、社会不安や未来への不安が出生数を押し下げているのかもしれない。
日本の「地方人口」は、国連のデータによると2018年からわずか12年間で17%減少するそうだ。世界でもトップクラスの人口減少のスピードになるそうだ。それでも、東京の合計特殊出生率は最も低い1.21人(2017年)。逆に、沖縄は1.94人(同)と最も高い。
少子化を阻止したいのであれば、大都会から地方への人口流出を促す、地方重視の政策に切り替えるしか方法はないのかもしれない。
著者:岩崎 博充