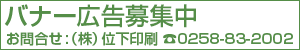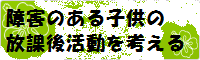「健常者は障害者に関わってほしい。障害者は、必要な支援を人に伝えられるようになろう」-。3月に卒業を控えた和光大現代人間学部4年の村竹陽太さん(22)=川崎市麻生区=が、こんな卒業論文をまとめた。最も重い「1級」の視覚障害があるが、周囲への取材や自身の実体験に基づいて、合理的配慮の在り方を提言。互いの交流が深まれば理解不足は乗り越えられる、と結論付けた。
中学生で発症した。野球部の守備で、飛んでくるボールが見えなくなっていく。中学最後の大会への出場もかなわなかったが、進学先の特別支援学校で同じ障害のある学友と交流。「目が見えなくても笑える」ことを知った。
今の視覚は光を感じられる程度。それでも東京・町田市にある大学キャンパスの近くで1人暮らしを続け、水泳部では平泳ぎの選手として大会にも出た。今は目が不自由な日々を、楽しむようにもしている。「コンビニで買ったおにぎりの具は、口に入れてのお楽しみ、とか」
一方、学生生活の中で、健常者と障害者の相互理解を巡る課題にも関心が深まった。「突然手を引かれると、怖い思いをすることもある」「慣れた駅なら、エレベーターよりも、点字付きの手すりのある階段で上り下りする方がいい」。友人と、そんな会話を交わしたことが発端だ。
都内の駅で降車時、ホームと車両の隙間に落ちたことがある。「周りにも似た体験をした人は多い」。視覚障害者がホームから転落する事故を、人ごととは思えない。
視覚障害のうち、全盲は一部にすぎない。残っている視力で可能なこと、必要な支援は多様のはずだ。交流の乏しさが、理解を阻む一因になっていないか-。
卒論のテーマが決まった。友人やアルバイト先の同僚ら10人ほどにインタビューを重ね、パソコンの音声読み上げソフトを駆使して原稿をまとめた。
善意のすれ違いを防ぐ策として盛り込んだ考察は、健常者が「お手伝いしましょうか?」という一声を掛けること。障害者にも判断の余地を残す響きがある、と感じたからだ。
ハンディの詳細に触れるのがタブーになりがちな風潮は「理解の壁」と指摘。双方に必要な意識の提言で論文を結んだ。「健常者は(障害者と)関わり、知ろうとすること。障害者は(自身の障害を)人に伝えられるようになること」
指導した竹信三恵子教授は「『見えている者に、見えないものがある』と気付かされる」。論文を「障害者差別禁止法施行などで障害者とともに働ける職場づくりが注目されている中、職場設計の視点で障害者を採用し、日常的に内側から改善する必要性を示唆している」と評価している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170226-00015997-kana-l14
[ カテゴリー:222掲示板 ]
交流深め、障害理解を 視覚障害の大学生が卒論で訴え
団体理念 │ 活動展開 │ 団体構成 │ 定款 │ プライバシーの考え方 │ セキュリティについて │ 事業 │ メディア掲載 │ 関連サイト │ お問い合わせ
copyright © JMJP HOT TOWN Infomaition Inc. All Rights Reserved. NPO法人 住民安全ネットワークジャパン
〒940-0082 新潟県長岡市千歳1-3-85 長岡防災シビックコア内 ながおか市民防災センター2F TEL:0258-39-1656 FAX:020-4662-2013 Email:info@jmjp.jp