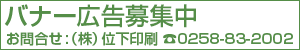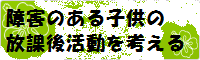水俣病に強い関心を持ち、熊本県と新潟県に1年ずつ滞在して患者らと交流しながら研究を進めてきた米国人女性がいる。ハワイ大大学院生のミッシェル・デイグルさん(32)。論文をまとめるため今月末に帰国するが、日本での経験を糧に、今後も水俣病とかかわっていくつもりだ。(深谷浩隆)
米・ニューハンプシャー州出身のデイグルさんは2004年から2年間、鹿児島県の小中学校で外国語指導助手(ALT)をしていた。1年目の冬に偶然、熊本県水俣市の水俣病資料館を訪れた。母国の教科書には載っていなかった事実を知り、衝撃を受けた。被害を伝える資料と、患者の少女の輝く瞳を捉えた写真、対照的に目の前に広がるきれいな海……。デイグルさんは「怖さと美しさを同時に感じ、もっと勉強したいと思った」と振り返る。
ALTをしながら水俣病の写真集や英語の文献を集めて学び、帰国後の08年秋に大学院に入ってからは、現地調査の許可を得るための勉強を重ねた。11年10月から水俣市で、12年10月から県内でそれぞれ1年間、社会人類学の見地から水俣病を調査した。係争中の裁判や行事にも足を運び、患者や支援者らと交流を深めた。両県で90人以上に聞き取り調査を行い、文献や新聞記事を収集した。
研究を通じ、自身が関心を持つきっかけとなった写真そのものが、他の患者を苦しめることもあることを実感した。重篤な患者の写真は見る人に強い印象を与える一方で、水俣病のイメージを固めてしまい、見た目では症状がわかりづらい多くの患者が認められる際のハードルになる。聞き取りをした患者の中には、感覚障害を説明するために、痛みを感じない体の部位を自ら傷つけて見せる人もいたという。
デイグルさんは、水俣病が当初「奇病」とされたことで構造的な差別が生まれ、新たに認定を求めようとした人たちが「ニセ患者」などといった偏見を持たれるようになったと指摘し、「水俣病は社会的につくられた苦しみとなっている」と語る。
論文の完成にはさらに3年ほどかかるといい、「患者が生きている限り、水俣病の問題は終わらない。これからも研究を続けていきたい」と力を込めた。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20131025-OYT8T01188.htm