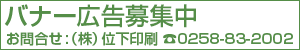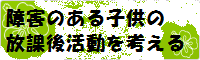一部の医療機関が計画している新型出生前検査の臨床研究。その目的の一つは遺伝カウンセリングの研究とされるが、遺伝カウンセリングとはどのようなものだろうか。
◆安心して迷える
日本認定遺伝カウンセラー協会の田村智英子理事は「出生前検査を受けるか、結果によって中絶するかは、妊婦やカップルが自分なりに情報を受け止めて決断していく。遺伝カウンセリングはその過程において、適切な情報を提供し、個人の価値観に基づく決断をサポートする」。
新型出生前検査の場合、妊娠10週から検査ができる。陽性だった場合、確定診断には15~16週頃から可能な羊水検査を受けることになり、検査結果が出るまで長くて2カ月かかる。中絶ができるのは妊娠22週未満という期限がある。
統計や確率、障害や病気の話をどう受け止めるかは個人によって異なる。検査によって、出産までに障害や病気の子供を受け入れる準備の時間となった人たちもいる。田村理事は「検査を受けるか、子供に医学的問題が見つかったときに中絶するか妊娠継続するか。どんな選択肢を選ぶとしても他の人に強いられることなく、安心して悩んだり迷ったりしながらその人らしい決断をしてほしい」と話す。
◆体制整備が急務
「国内の相談体制は絶対的に不足している」と指摘するのは、東京大学死生学・応用倫理センター(東京都文京区)の小椋宗一郎研究員(倫理学)だ。
遺伝カウンセリングの担い手は臨床遺伝専門医と認定遺伝カウンセラー。12月1日現在、臨床遺伝専門医は970人、認定遺伝カウンセラーは139人。だが、臨床遺伝専門医のうち産婦人科医として出生前検査にかかわる医師は限られる。認定遺伝カウンセラーとしての就労は少なく、カウンセリング技術を磨く場も少ないのが現状だ。
ドイツでは、遺伝子検査前のカウンセリングを法律で義務付けている。小椋研究員によると、医師による説明のほか、国内1500カ所以上に妊娠相談所が設けられ、研修を積んだ相談員が無料で対応している。
医学的な情報提供も行うが、検査の結果や不安、動揺をどう受け止めたらいいかなど妊婦の心情に寄り添う。妊婦のパートナーや親との関係、経済的事情などの社会的な相談にも乗るのが特徴だ。障害者援助団体や親の会も紹介し、具体的な支援も行う。
日本では、カウンセリング体制が整わないまま出生前検査を実施している医療機関も多いとみられる。だが、医療機関側も経営難や医師不足など体制整備できない事情もある。
日本産科婦人科学会は近く、新型出生前検査の指針を発表する見込みだが、指針に強制力はない。臨床研究で導入される米国・シーケノム社以外にも新型検査を扱う企業はあり、相談体制が整わないまま検査を行う医療機関が出てくる懸念もある。妊婦をサポートするには検査の提供と並行して質の高い相談体制を整備することが急務だ。情報提供のあり方も考えるべきだ。
小椋研究員は「日本の妊娠相談について、医療機関が体制を整えやすいように国も施策を打ち出すべきだ」と指摘している。
■悔いのない決断を支援
出生前検査をめぐっては中絶を考慮する夫婦の支援も必要だ。
北里大学(相模原市南区)の斎藤有紀子准教授(生命倫理学)は「どんな子供でも産もうと決めている人は最初から検査を受けないこともある。検査を受け、確定診断まで行う人には、出産を迷う人が多くなるだろう」と話す。出産も中絶も女性の心身に負担を伴う。出生前検査で胎児の障害が分かったとき、適切な情報提供や社会資源の紹介、揺れ動く心のサポートが悔いのない決断の支えとなる。
斎藤准教授は「産むことの支援は語られやすいが、中絶のサポートはタブーになりやすい。中絶を決めた後も迷い続ける人、中絶をやめる人もいる。産まない決断を支えることは産む決断を支えることにもつながる。医療者は妊婦を最後まで支える体制を整えてから検査をすべきではないか」としている。
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/life/medical/snk20121216507.html