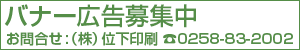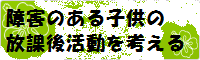この20年間に、途上国を含め人類は幼少期の死亡が減少する一方で、生活習慣病など病気を抱えながら長生きするようになったことが、日本を含む国際チームの調査で分かった。世界全体で疾病構造が激変したことを示しており、高齢化に伴う生活習慣病を中心とした保健医療政策が求められそうだ。14日付の英医学誌ランセット(電子版)に発表した。
187カ国の死亡や病気のデータなどを分析した。その結果、1990年の出生1000人当たりの5歳未満死亡率は男8%、女6.6%だったのに対し、2010年には男4.7%、女3.9%に減少していることが分かった。理由として、経済成長に伴う栄養の改善やワクチンの普及などを挙げた。
平均寿命は男67.5歳、女73.3歳で、20年前より4.7歳、5.2歳延びた。特に途上国が顕著で、インドなど南アジアは男63.4歳、女67.7歳と5.8歳、8歳それぞれ延びていた。
また、2010年のけがや病気による治療期間など苦しみを独自に指標化すると、最も高かったのは虚血性心疾患(狭心症など)で、肺炎、脳卒中と続いた。1990年の上位3位は肺炎、下痢、未熟児合併症だった。心疾患や脳卒中は肥満や高血糖などに起因することが多く、生活習慣病による社会影響が深刻化していることを示した。このほか、エイズは33位から5位に、うつ病は15位から11位に上昇した。
チームの渋谷健司・東京大教授(国際保健政策)は「これまで感染症対策を重点にしていた。これからは、生活習慣病や精神疾患の対策も視野に入れた保健医療に変えていく必要がある」と話す。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121214-00000022-mai-soci